ターゲット分析は難しいね
売上は増えているものの利益が伸び悩んでいるとかいう
企業があるかと思います。
自分の所属する業界では原価低減をしてもその分、顧客側で
単価下落圧力がかかり、
更に利益が悪化して原価を低減して利益を確保しようとすると・・
更に価格下落が続いてという悪循環となっているケースでどうすれ
いいのかと思って考えてみました。
営業経験は全くないですが、自社の営業の顧客分析手法を
整理してみて考察してみました。
色々と非難もあるかもしれませんが、考え方の一つとして
暖かく見守っていただければ幸いです。
1:通常の分析について
(1)ステップ1=顧客分析 <どれだけ売れているか>
1)売上高、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年利益
3)前年売上高比、前年利益比
上記の3つの数値を分析し前年比でどれだけ成長しているかを
分析する。自分が担当している得意先で構成比を出して
構成比が高く前年比が増加している先をターゲットとする。
→ターゲット先は与信上問題ないものと考える。
(2)ステップ2=商品別分析 <どんな商品が売れているか?>
商品毎に下記の分析をして売れ筋を把握する。
1)売上高、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年利益
3)前年売上高比、前年利益比
伸びている商品群について分析し、その商品についての
オプションを見直してアップセルを働きかける。
また売行きが弱い商品群についてクロスセルを働きかけて
ついで買いを誘発させる。
おおむね上記のようなステップで物を売ろうとしているみたいです
*
2:自分なりに考えてみたプロセス
(1)ステップ1=顧客分析 <どういう傾向の会社か>
1)売上高、自社売上原価、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年自社売上原価、前年利益
3)前年売上高比、前年自社売上原価比、前年利益比
4)得意先の貸借対照表(商品関連、買掛金、繰越利益剰余金)
2年分を見て前年の金額ベースと比較→帝国データバンク等使用
5)得意先の損益計算書(売上高、売上原価、売上総利益)
2年分を見て前年の金額ベースと比較→帝国データバンク等使用
3)を分析する。特に前年利益比で成長できているかを確認
4)の繰越利益剰余金を見て上昇基調か確認。5)で売上原価が
増えて売上高が増えて売上総利益が増えているかを確認。
→自社が利益を取れていて、売上原価が増えていれば
単純に考えれば自社の商品をもう少し販売してもらえる(
(2)ステップ2=得意先をランク分けする。 <お客様はどんなのか?>
A=自社、他社とも扱っていて売上高↑、売上原価↑
売上利益↑の場合(繰越利益剰余金↑)=優良先
B=自社、他社とも扱っていて売上高↑、売上原価↓
売上利益↑の場合=値引を強く求められる可能性大
C=自社のみ扱っていて売上高↑、売上原価↑
売上利益↑の場合(繰越利益剰余金↑)=維持先
D自社のみ扱っていて売上高↑、売上原価↓
売上利益↑の場合=不良顧客
Aの顧客はシェア争いのため価格に走りがちだが、商品差別化
で他社と棲み分けを図りシェアを維持する戦略にて利益確保を
検討する必要がある。
Bについては値引を強く求められる可能性があるため、今後の
方針をきちんと検討する必要がある。
いいが値引圧力が高まるため注意が必要、Dに関しては取引条件を
含めて見直した上で販売戦略を再検討する必要がある。
(3)ステップ3=商品別分析 <どの商品で利益が取れているか>
商品毎に前年との比較をしてどの商品が増加傾向にあるかを
分析する。
1)売上高↑、利益↑
2)売上高↓、利益↑
3)売上高↑、利益↓
4)売上高↓、利益↓
1)の商品群については売行き好調なので売上を拡大できれば
望ましいが、先行きに注意が必要
2)に関しては利益が取れておりこのまま維持できればいいが
売上が下落基調となる可能性もあるため販促等も考えないと
厳しい。得意先へのヒアリングも必要
3)に関しては適正利潤を確保できる様に誘導できればいいが
値引き圧力が更に高まる可能性が高いので代替品の検討も必要。
4)
(4)ステップ4=クロス分析 <どの顧客でどの商品を販売するか?>
Bランクの顧客とCランクの顧客について重点的に分析を行う。
特にBランク顧客については3)と4)の販売を絞り込んで1)
誘導して売上拡大を図る必要があるものと思われる。
Cランクの顧客については4)の供給をやめてしまい。
1)、2)
Aについては2)
商品を進める施策を検討する必要がある。
Dについては4)の商品の供給をストップし3)と2)
取引自体を検討していく必要がある。
当てはまらないよとかそんな単純じゃないよという意見もあるかも
しれません。分析も複雑になるし、
あるんですが、
して再度分析することで、
思って書いてみました。
分析については人手でやってたらきりがないんでシステムで自動化
視覚的にとらえて戦略を練れる様にできれば、営業マンの負荷が
下がるのではないでしょうか?
売上予算を検討するときにもセグメンテーションの構成比で自分の
目標売上を配分してやれば、
なっていれば少しは営業マンも楽になるかもしれないと思いますが
いかがでしょう?
最後に昨今の経営者はBが望ましいモデルと思っている節が
有るのではないかと思います。原価低減にも限りがあり、
取引先にも原価低減を要求すると相手先の利益を減らす。
更にモノが売れなくなるという悪循環がずっと続いてしまうのでは
と思います。
Bの様な企業が減ってAの様な企業が増えれば皆がハッピーに
なれるのではないかなと思った次第です。
長文の上、分かりにくかったらすいません。(笑)
企業があるかと思います。
自分の所属する業界では原価低減をしてもその分、顧客側で
単価下落圧力がかかり、
更に利益が悪化して原価を低減して利益を確保しようとすると・・
更に価格下落が続いてという悪循環となっているケースでどうすれ
いいのかと思って考えてみました。
営業経験は全くないですが、自社の営業の顧客分析手法を
整理してみて考察してみました。
色々と非難もあるかもしれませんが、考え方の一つとして
暖かく見守っていただければ幸いです。
1:通常の分析について
(1)ステップ1=顧客分析 <どれだけ売れているか>
1)売上高、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年利益
3)前年売上高比、前年利益比
上記の3つの数値を分析し前年比でどれだけ成長しているかを
分析する。自分が担当している得意先で構成比を出して
構成比が高く前年比が増加している先をターゲットとする。
→ターゲット先は与信上問題ないものと考える。
(2)ステップ2=商品別分析 <どんな商品が売れているか?>
商品毎に下記の分析をして売れ筋を把握する。
1)売上高、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年利益
3)前年売上高比、前年利益比
伸びている商品群について分析し、その商品についての
オプションを見直してアップセルを働きかける。
また売行きが弱い商品群についてクロスセルを働きかけて
ついで買いを誘発させる。
おおむね上記のようなステップで物を売ろうとしているみたいです
*
2:自分なりに考えてみたプロセス
(1)ステップ1=顧客分析 <どういう傾向の会社か>
1)売上高、自社売上原価、利益=(売上高-自社売上原価)
2)前年売上高、前年自社売上原価、前年利益
3)前年売上高比、前年自社売上原価比、前年利益比
4)得意先の貸借対照表(商品関連、買掛金、繰越利益剰余金)
2年分を見て前年の金額ベースと比較→帝国データバンク等使用
5)得意先の損益計算書(売上高、売上原価、売上総利益)
2年分を見て前年の金額ベースと比較→帝国データバンク等使用
3)を分析する。特に前年利益比で成長できているかを確認
4)の繰越利益剰余金を見て上昇基調か確認。5)で売上原価が
増えて売上高が増えて売上総利益が増えているかを確認。
→自社が利益を取れていて、売上原価が増えていれば
単純に考えれば自社の商品をもう少し販売してもらえる(
(2)ステップ2=得意先をランク分けする。 <お客様はどんなのか?>
A=自社、他社とも扱っていて売上高↑、売上原価↑
売上利益↑の場合(繰越利益剰余金↑)=優良先
B=自社、他社とも扱っていて売上高↑、売上原価↓
売上利益↑の場合=値引を強く求められる可能性大
C=自社のみ扱っていて売上高↑、売上原価↑
売上利益↑の場合(繰越利益剰余金↑)=維持先
D自社のみ扱っていて売上高↑、売上原価↓
売上利益↑の場合=不良顧客
Aの顧客はシェア争いのため価格に走りがちだが、商品差別化
で他社と棲み分けを図りシェアを維持する戦略にて利益確保を
検討する必要がある。
Bについては値引を強く求められる可能性があるため、今後の
方針をきちんと検討する必要がある。
いいが値引圧力が高まるため注意が必要、Dに関しては取引条件を
含めて見直した上で販売戦略を再検討する必要がある。
(3)ステップ3=商品別分析 <どの商品で利益が取れているか>
商品毎に前年との比較をしてどの商品が増加傾向にあるかを
分析する。
1)売上高↑、利益↑
2)売上高↓、利益↑
3)売上高↑、利益↓
4)売上高↓、利益↓
1)の商品群については売行き好調なので売上を拡大できれば
望ましいが、先行きに注意が必要
2)に関しては利益が取れておりこのまま維持できればいいが
売上が下落基調となる可能性もあるため販促等も考えないと
厳しい。得意先へのヒアリングも必要
3)に関しては適正利潤を確保できる様に誘導できればいいが
値引き圧力が更に高まる可能性が高いので代替品の検討も必要。
4)
(4)ステップ4=クロス分析 <どの顧客でどの商品を販売するか?>
Bランクの顧客とCランクの顧客について重点的に分析を行う。
特にBランク顧客については3)と4)の販売を絞り込んで1)
誘導して売上拡大を図る必要があるものと思われる。
Cランクの顧客については4)の供給をやめてしまい。
1)、2)
Aについては2)
商品を進める施策を検討する必要がある。
Dについては4)の商品の供給をストップし3)と2)
取引自体を検討していく必要がある。
当てはまらないよとかそんな単純じゃないよという意見もあるかも
しれません。分析も複雑になるし、
あるんですが、
して再度分析することで、
思って書いてみました。
分析については人手でやってたらきりがないんでシステムで自動化
視覚的にとらえて戦略を練れる様にできれば、営業マンの負荷が
下がるのではないでしょうか?
売上予算を検討するときにもセグメンテーションの構成比で自分の
目標売上を配分してやれば、
なっていれば少しは営業マンも楽になるかもしれないと思いますが
いかがでしょう?
最後に昨今の経営者はBが望ましいモデルと思っている節が
有るのではないかと思います。原価低減にも限りがあり、
取引先にも原価低減を要求すると相手先の利益を減らす。
更にモノが売れなくなるという悪循環がずっと続いてしまうのでは
と思います。
Bの様な企業が減ってAの様な企業が増えれば皆がハッピーに
なれるのではないかなと思った次第です。
長文の上、分かりにくかったらすいません。(笑)
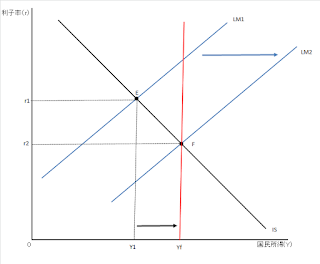
コメント